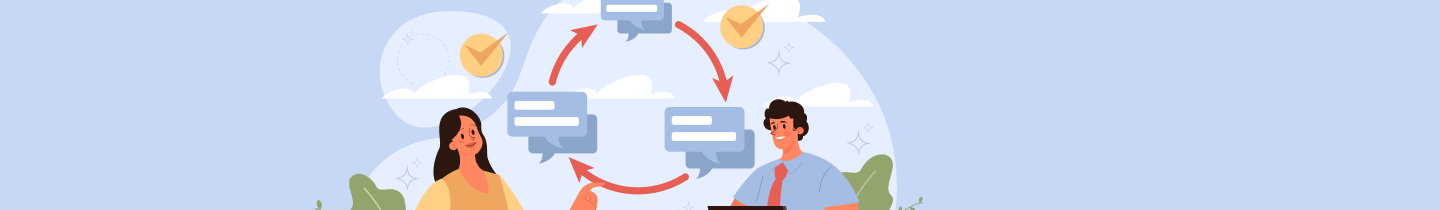
新規プロジェクト担当者、必読! #04
「ユーザーの声、どこにある?」仮説検証に効くヒアリング設計術
営業トークにもめちゃくちゃ活用できる、ユーザーの“声”の拾い方。
最終更新日:2025年7月4日
仮説は立てた、でも「誰に」「何を」聞けばいい?
新しい施策や商品の企画段階では、よく「まずは仮説を立てよう」と言われます。
でも、その仮説、実際に“誰に”聞いて、“どう”確かめればいいのでしょうか?
相手を間違えたり、聞き方を誤ったりすれば、せっかくの検証もただの確認作業で終わってしまいます。
大事なのは、「本当に違いが見える問い方」をすること。
そして──
実はこのヒアリング設計の考え方、営業トークの設計にも応用できる視点なんです。
ユーザーの声を“聞きに行く”のが難しい理由
「顧客の声を聞きましょう」
この言葉を鵜呑みにすると、つい“近くにいる人”ばかりに話を聞きに行ってしまいます。
でも、仮説検証の相手として適切なのは、
「自分たちの答え合わせをしてくれる人」ではなく、「ズレを起こしてくれる人」かもしれません。
さらに、ヒアリングを難しくしているのは、以下のような背景です。
- 答えを持っていそうな人が誰か、そもそも明確ではない
- 「とりあえず既存顧客に聞く」が無難だけど、それでは仮説の視野が広がらない
- 「正解」を聞こうとすると、会話が詰まる or お世辞の返答で終わることも
仮説タイプ別に考える、聞くべき相手の選び方
仮説にもいろんなタイプがあります。
どんな問いを立てているかによって、「誰に聞くか」も変わってくるのです。
顕在層向けの仮説 → 既存顧客 or 失注顧客
「この機能を追加すれば、今のユーザーにもっと使ってもらえる」
といった、明確な改善仮説を立てたなら、実際にそのユーザーだった人に話を聞くのが正攻法です。
潜在ニーズ仮説 → 検討層 or 非顧客
「今は使っていないけど、こういう人たちもニーズがあるのでは」
そんな仮説なら、今まで接点のなかった層にも声をかけてみるべきです。
例えば、アンケート配信サービスやSNSのDMなども手段になります。
否定されやすい仮説 → あえて“懐疑派”に聞く
自分たちが少数派だと感じている仮説なら、あえて否定しそうな層にぶつけてみる。
賛同を得るよりも、「なぜ刺さらないか」の反応から学べることは多いです。
設問は「YES/NO」より「反応の差」で設計する
問いの立て方ひとつで、相手の反応の深さは変わります。
ヒアリング設計では、「答えが明快になるか」ではなく、「反応に差が出るか」で考えるのがコツです。
たとえばこんな設問は有効です:
- 「もし〇〇が突然使えなくなったら、何に困りますか?」
- 「今のやり方に“強いて言えば”どんな違和感がありますか?」
- 「これはあった方がいい、と思う人と、そうじゃない人がいるとしたら、なぜだと思いますか?」
これらの質問には、
- “言いづらい違和感”を言語化するきっかけになる
- 賛否が分かれたときに「誰に、なぜ刺さる/刺さらない」が見えてくる
という効果があります。
実践ミニワーク ヒアリング設計テンプレ
試しにちょっと下のテンプレートを利用して、仮説ごとにヒアリング設計を整理してみましょう。
項目 | 考えるべきポイント |
仮説の主旨 | 今、自分たちが仮に信じていること(例:○○な人は××を求めている) |
聞くべき対象 | 既存顧客/非顧客/検討層/否定派など |
使いたい質問 | 「どんな時に…?」「なぜそう感じたんですか?」など温度が見える問い |
想定される反応 | 肯定/否定/困惑など、分かれるポイントがどこか |
仮説スプレッドとは?
1つの仮説に対して、「誰に」「何を」「どう聞くか」を整理するための簡易設計表。ヒアリング対象や質問内容のブレを防ぎ、“とりあえず聞いてみた”を避けるために有効。
仮説は、壊して、育てていくもの
仮説検証とは、“正解にたどり着く”ための作業ではありません。
むしろ、「ちょっとズレてたかも」「こういう見方もあるのか」という違和感に出会うことが大事。
仮説は、当たっているかどうかよりも、
“人の反応を引き出せる問い”にできているかが、良い検証のカギです。
この視点は、実は営業のヒアリングにもそのまま活きます。
仮説をベースに、顧客の反応を見ながら“対話の切り口”を変えていく──
そんな柔軟な営業スタイルにも、この記事の考え方はきっと役立つはずです。
