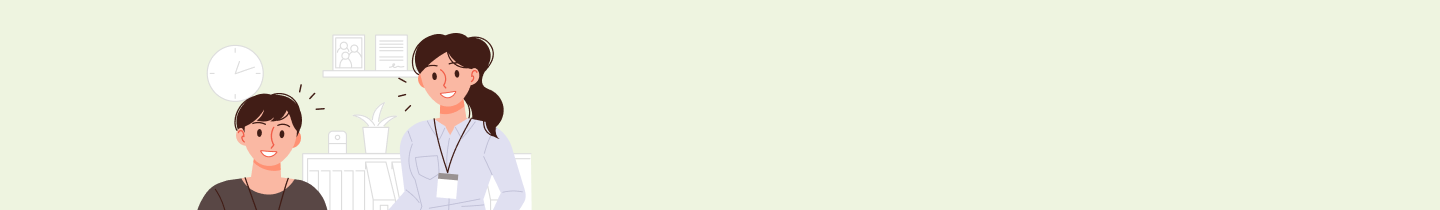
新規プロジェクト担当者、必読! #10
「何やってるか分からない」と言わせない、進捗共有が信頼を生む理由
“成果”ではなく“見える化”こそが信用残高になる。
最終更新日:2025年10月1日
実績が出る前に、信頼される人は何をやっている?
新しいプロジェクトを立ち上げて、ようやく少しずつ動き始めた。
ゆっくりとではあるけど、前進している実感はある。でも──
「あの人、今なにやってるんだろう?」
「なんか忙しそうだけど、どうなってるのかよく分からない…」
社内にそんな空気が流れていること、ありませんか?
成果が出る前のタイミングほど、
自分が“何をしているか”を可視化することが信頼をつくります。
その最もシンプルで効果的な方法が、「進捗の共有」です。
信頼は「成果」ではなく「透明性」から始まる
人は、目に見えないものを信じづらいもの。
ましてや新規プロジェクトは、数字や実績が出るまでに時間がかかる。
でも、今どんな仮説を考えていて、どんな動きをしていて、何に迷っているのか──
そうした“途中経過”が見えるだけで、周囲の安心感はまったく違います。
完成していなくても、オチがない話でも、迷いがある状態でも、
「見える」、それこどが信頼の入口。
言い換えるなら、透明性の積み重ねが信用残高になると言えます。
この「信用残高」という言葉は、
もともと証券取引や会計の世界で使われる用語で、
「信用取引の余力」や「貸方の残高」などを意味します。
本記事ではこの言葉を借りて、
“目には見えない信頼の預金”のようなものとして使っています。
たとえば、日々のSlackでの一言、社内報での共有、雑談の中でのひとこと──
そうした小さな発信の積み重ねが、
やがて「この人はちゃんと動いてる」「任せても大丈夫」という
“静かな信頼”を築いていく基盤になる。
それがここで言う“信用残高”です。
“進捗共有”の3つの効果
1.「存在感」が生まれる
Slackや社内報などで定期的に進捗を共有していると、
「何をやっている人か」が、自然に周囲に伝わっていきます。
誰かに“話しかけてもらえる状態”をつくるには、まず自分の輪郭を出すこと。
「見えている人」は、それだけでアクセスされやすくなるんです。
2.「巻き込み力」が高まる
進捗共有を続けていると、
「その件なら相談してみたい」「ちょっと協力できるかも」と、
周囲が“関わりしろ”を感じてくれるようになります。
情報を閉じている人より、開いている人のほうが、仲間になりやすい。
共創の種は、情報開示から芽吹きます
3.「思考の整理」になる(自分にとっても)
共有することは、考えを一度“人に伝える形”に変換する行為。
曖昧なまま進めていたものも、書くことで見えてくることがあります。
- 今、自分が何に悩んでいるか
- 何が進んでいて、何が止まっているのか
- どこに他者の視点や助けが欲しいのか
情報発信は、思考の振り返りでもあります。
“進捗共有”は、こうすると効果的──3つの視点から
1.「途中報告」でOK。完成を待たない勇気
「これから◯◯を試してみます」
「ちょっとここで悩んでます」
「今日◯◯にトライして、反応はこんな感じでした」
進捗共有は、「完成したもの」や「正解」だけを出す場ではありません。
むしろ“途中経過”こそが、周囲に「この人、ちゃんと動いてるな」と思ってもらえる材料になるんです。
- 失敗も、迷いも、成長プロセスの一部として見せる
- “アウトプット志向”よりも、“プロセス開示志向”で考える
- 迷っていることを開示すると、自然にフィードバックが集まりやすくなる
途中報告は、
「自分の進行状況を誰かと共有しようとしている姿勢」そのものが信頼を生むのです。
2.「定期投稿」で、“信頼の習慣”をつくる
一度の大きな共有よりも、小さな共有を“続けている人”の方が信頼されます。
- Slackチャンネルで週1投稿する
- Notionや社内報で「今週の進み具合」を書く
- 「〇〇進行中です!」だけでもOK
定期性があることで、周囲は「いつ更新されるか」を無意識に期待します。
そしてその期待が裏切られなければ、「この人は信頼できるな」と感じてもらえる。
継続=信頼の証明です。頻度は週1〜隔週でもOK。
決まった曜日に“軽く投稿”するだけで、存在感は倍増します。
3.「温度感」をにじませると、人が寄ってくる
「ちょっと焦ってます(笑)」
「ここは楽しんでやれてます」
「あ、これはちょっと手応えあるかも…!」
そんなふうに、状況報告だけでなく、
今の自分の“感情の温度”を添えると、グッと共感が生まれます。
- 無機質な報告ではなく、“人間っぽさ”がにじむ投稿にする
- 感情表現があると、「あ、あの人に声かけてみようかな」が起きやすくなる
- 結果的に、Slackでの軽い会話や偶発的なコラボが生まれやすくなる
温度感は、人と人との「心理的な距離」を縮める最短ルートです。
小さな見える化が、信頼をつくる
「自分(たち)はちゃんとやっている(つもり)」では伝わりません。
「動いてることを伝える」ことで、相手の安心につながり、
それが、「あの人に任せておけば大丈夫」につながっていくのです。
実績がない立ち上げ期というフェーズだからこそ、
“共有の丁寧さ”が信頼のバロメーター。
信用は、進捗という名の“小さな発信”から積み上がるんです。
今日の共有が、来週の協力を生み、1ヶ月後の味方を育てるかもしれません。
だからこそ、「何も進んでないから出せない」ではなく、
「出すことで信頼が積み上がる」という逆算の発想を持ってみてください。
