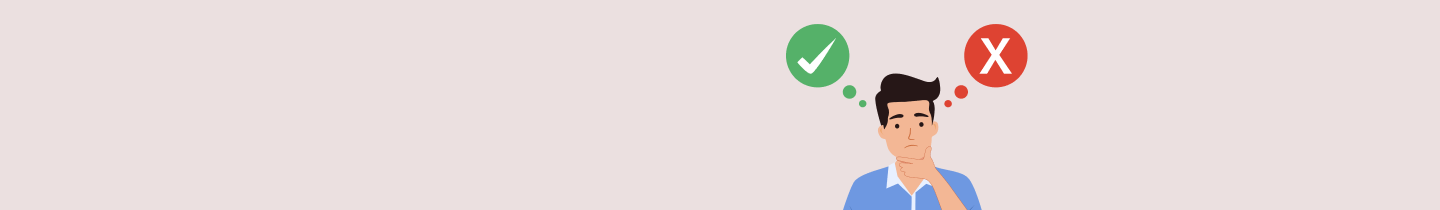
新規プロジェクト担当者、必読! #05
ベネフィットが伝わらない時の“価値の翻訳”入門
「わかる」では動かない──“伝え方のズレ”を埋める資料構成と思考のコツ
最終更新日:2025年8月28日
ちゃんと資料を作ったのに、なぜ響かない?
提案資料や社内上申資料をしっかり準備したのに、
上司やクライアントに「うーん・・・で、これって何がいいの?」と
首をかしげられた経験はありませんか?
言いたいことは明確だったし、資料にはわかりやすい図も入れた。
説明も丁寧に上手くできたはず──なのに、相手の反応は薄い。
──その原因は、「伝え方が下手だった」のではなく、
“価値の翻訳”ができていなかったのかもしれません。
「翻訳」とは、“相手の文脈”に合わせて価値を並べ替えること
多くの場合、人は「何ができるか」「どんな機能があるか」から話し始めてしまいがち。
だからこそ、提案資料や営業資料では、
こうした“Feature(機能・特長)”が主語になることがよくあります。
でも、それが相手にとって“なぜ良いのか”が見えていなければ、
単なる機能説明にしか聞こえず、相手の頭にも心にも届きません。
たとえば──
NG例:「このツールは、〇〇データを自動で取得し、月次で集計・レポート化できます」
OK例(翻訳後):「これまで人手で4〜5時間かかっていたレポート作成を、ミスなく自動化できるので、 “あの報告、まだですか?”と言われるプレッシャーから解放されます」
ポイントは、“機能”を“未来の変化”に変換すること。
そして、その変化が“誰にとってどう嬉しいか”を、相手の立場で語ることです。
営業も企画も、翻訳者である
価値の翻訳とは、単なる言い換えではなく、
情報の構造と順番を再設計する思考法です。
- 誰に対して
- どんな状況で
- どんなストレスや課題を持っている人に対して
それに応じて「何を前に出し」「何を省き」「何を例に挙げるか」を組み替えていく。
この考え方は、顧客向けの提案資料だけでなく、
社内プロジェクトの稟議資料や
関係部署への共有ドキュメントにもそのまま応用できます。
伝え方を変える“翻訳フレームワーク”3選+具体例
ここからは、実際に使える“価値の翻訳”のための
3つの構成フレームと、その活用例を紹介します。
① FAB(Feature → Advantage → Benefit)
- Feature(特徴・機能):〇〇データを自動収集
- Advantage(利点):集計の手間が省ける
- Benefit(価値):ミスなく早く報告できる→他の仕事に集中できる
Before(翻訳前)
「毎月〇〇データを自動で集計し、CSV形式で出力可能です」
After(翻訳後)
「月初の集計作業が自動化され、営業部門では“数字まとめ”の工数がゼロに。月初1日目から分析やアクションにつなげられます」
→ 「で、何が良いの?」を先回りして言語化するのがFABの真骨頂です。
② ゴールデンサークル(Why → How → What)
- Why(なぜ):今、部門間の情報連携が課題
- How(どうやって):全体可視化と一元化を実現するツールで
- What(何を提供):共有ダッシュボード+アラート機能
Before(翻訳前)
「このツールでは、各部署のKPIを一元表示できます」
After(翻訳後)
「情報がバラバラで会議が空回りしていた状況を、“可視化”と“通知”で改善。“何を、いつまでに、誰がやるか”が、すべての部署でズレなく共有できるようになります」
→ “How”や“What”から始めない。Whyから話せば、聞き手のモードが変わります。
③ ストーリー型構成:Before → 課題 → 解決 → After
- Before:導入前の“困っていた状態”
- 課題:何が原因で、どう不便だったか
- 解決:それに対して、どんな打ち手をしたか
- After:結果、どう変わったか/何が生まれたか
- Before(翻訳前)
「AIによる文書分類機能があり、手動分類のミスを防げます」 - After(翻訳後)
「過去は1件ずつ手作業で分類していたため、月末は“確認と修正”だけで1日が終わっていました。AIの自動分類を導入した結果、最終チェックだけで済むようになり、月末処理にかかる時間が半分になりました」 - → 提案資料だけでなく、社内報告・導入事例・ナレッジ共有資料にも応用できる構成です。
FABとは?
FABは、営業やマーケティングで使われる説明のフレームワーク。「Feature(特徴)→ Advantage(利点)→ Benefit(価値)」という順番で伝えることで、機能だけでは伝わらない“意味”を相手に理解させる。機能紹介で終わらず、相手の状況に応じた価値を導き出せるのが特徴。
結局、“3秒で伝わる”かどうかがすべて
人は、最初の数秒で「読むか・読まないか」「聞くか・流すか」を判断します。
だからこそ、資料や提案の冒頭に
“翻訳された価値”が入っているかどうかが、勝負の分かれ目。
- 「誰のどんな困りごとが、どう楽になるのか」
- 「それによって何が生まれるのか」
- 「あなたの“次の動き”は、どれだけ軽くなるのか」
この視点を入れて資料をつくるだけで、相手の反応は明らかに変わってきます。
価値は、“伝える”より“伝わる構造”でつくる
企画が通らない、資料が読まれない、提案が響かない――
それは、“中身が弱い”のではなく、“構造が翻訳されていない”だけかもしれません。
- 相手の立場に合わせて
- 順番を変えて
- 未来の変化に変換して伝える
すべての仕事は、「誰かに意味を届けること」。
だから私たちは、翻訳者としてのスキルを
もっと意識的に伸ばし、活用していくべきだといえます。
